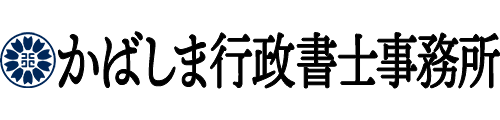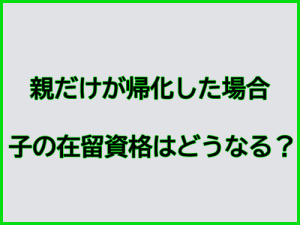民泊申請“消防法令適合通知書”交付までの流れ
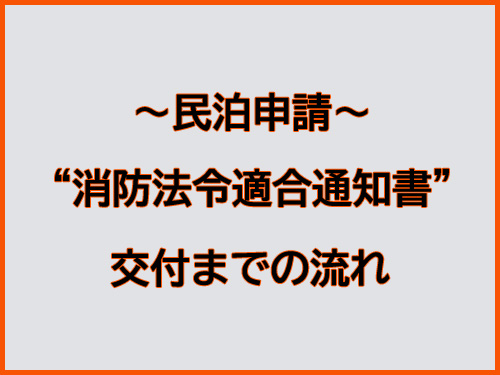
先月に受任が決まった住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出案件の事前相談で、管轄の保健所と消防本部へ行きました。
ご存知の通り、旅館業も含め民泊事業に於いては、それぞれの法律での規制以外にも、各自治体による独自のルールが存在します。
大まかな概要は、各自治体のホームページなどで確認することは出来ますが、やはり詳細な部分を把握するには、この事前相談での個別具体的な確認が不可欠です。
保健所の相談では、手続き全体の流れや図面に必要な面積の種類などの説明を。
あくまで、今回担当する物件に於いて…という前提ですが、平面図も下記の3種類の面積の算出と記入が必要になります。
・部屋全部の内寸(押し入れは除外)
・寝室部分の壁芯(押し入れは除外)
・寝室以外の全ての壁芯(押し入れも含む)
ちなみに、自動火災報知器や消化器等の消防設備関連の設置場所や、避難ハシゴを取り付けの場合には、立面図は必要になることもありますし、誘導灯の配線図も必要になります。
そして、もう1つは“消防法令適合通知書”を申請時の添付書類として提出するように…と。
ということで、消防署での事前相談で詳しく確認をしてきました。
担当物件の地域性もあるかもしれませんが、想定していたよりも規定が細かく厳しいなという印象。
全部屋に設置する自動火災報知器の設置場所、消火器のタイプ、誘導灯の設置場所、上階へ設置する避難ハシゴ等の確認をしつつ、消防設備の取り付け業者のご紹介もして頂けました。
そして、この消防設備の取り付けも、勝手に始めることは出来ません。
まずは、着工届(工事整備対象設備等着工届出書)を提出します。
消防法令に基づき消防用設備等を設置する際は、消防設備士の資格を持った者が行う必要がある場合があります。
工事を行う消防設備士は、工事着手の10日前までに“工事整備対象設備等着工届出書”を管轄消防署に提出します。
※着工届が不要となる設備についても別途“消防用設備等設置届出書”の届出が必要になるケースもあります。
消防用設備等の設置が終わったら、設置届(消防用設備等設置届出書)を提出します。
これは、設置工事が完了した日から4日以内に管轄消防署に“消防用設備等設置届出書”を提出します。
更には、建物の収容人員が30人以上となる場合は、防火管理者の選任及び消防計画の作成及び届出“防火管理者選任届出書”が必要となり、市町村等の火災予防条例によっては“防火対象物使用開始届出書”の提出が必要となる場合があります。
諸々の設置が完了しましたら、申請(届出)時に必要な“消防法令適合通知書”の交付申請をするという流れになります。
■消防法令適合通知書の交付までの流れ
1.消防法令適合通知書の交付申請
※管轄消防署へ所定の様式により、交付申請します。
2.消防法令適合状況の調査
※管轄消防署により、立入検査等を実施し、消防法令への適合状況について調査します。
3.消防法令適合通知書の交付
※調査の結果に基づき、消防法令に適合していると認められたら、ようやく“消防法令適合通知書”の交付となります。
多くの物件が、民泊事業へ向けてのリフォームを行うかと思いますが、リフォーム後に消防設備の取り付けを手配するのか、あるいは並行して行うのか、クライアントの希望を聞きつつ、スムーズな段取りを提案することも、とても重要になってきますね。
樺島 誠二 / プロフィール

- 申請取次行政書士・樺島 誠二(第24091486号)
- 【行政書士✕プロドラマー】
神奈川の二刀流行政書士・樺島 誠二です。
ビザ申請、帰化申請等の国際業務や、民泊申請をメインに、開業2年目ながら、既に多くの案件を受任。
迅速且つ確実な申請サポートを提供します。
また、沢木優の名義でプロドラマーとしても活動中(Pearl Drums、Vic Firth社のモニターアーティスト)です。
2002年にメジャーデビュー後、レコーディングやライヴのサポート、ドラム講師など…数々のドラム仕事を経験。
2024年3月には、New Yorkブロードウェイミュージカル「WITHOUT YOU」来日公演にてツアードラマーを務めました。
最新の投稿
 行政書士2025年12月31日大きく前進した2025年~開業1年半のリアル
行政書士2025年12月31日大きく前進した2025年~開業1年半のリアル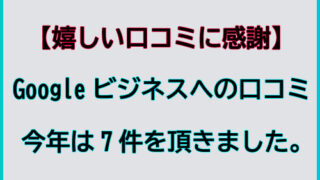 お知らせ2025年12月30日嬉しい口コミに感謝!!
お知らせ2025年12月30日嬉しい口コミに感謝!! ドラマー2025年12月29日Happyが満載な日曜日
ドラマー2025年12月29日Happyが満載な日曜日 ドラマー2025年12月26日クリスマスも二刀流🎄
ドラマー2025年12月26日クリスマスも二刀流🎄