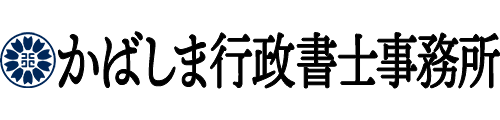市街化調整区域での住宅宿泊事業について
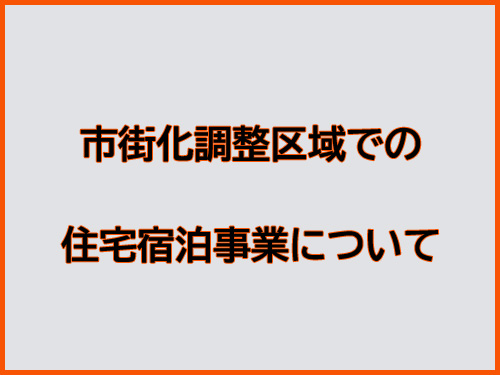
住宅宿泊事業については、各自治体による様々なローカルルールが存在します。
その1つに、住宅宿泊事業を行う際の制限区域というものがあります。
例えば、都市計画法第8条第1項第1号に規定する低層住居専用地域や、中高層住居専用地域など…。
今回は、市街化調整区域に設定されている地域で、住宅宿泊事業を展開することは可能なのか?という部分にフォーカスして書いていきます。
■そもそも市街化調整区域とは
市街化調整区域とは、都市計画法に基づいて指定された地域です。
無秩序な都市化を防ぐため、市街化を抑制するためのものです。
この市街化調整区域内では、住宅の建築や用途の変更などが厳しく制限されています。
この区域内で新規で住宅を建築する場合、又は既存の建物の用途を変更する場合は、原則として開発許可が必要になります。
この開発許可の審査は大変厳しく、都市計画に適合しているか細かくチェックされます。
よって、市街化調整区域内で民泊事業を展開するのは、通常の市街地に比べると、やや難易度は上がるかなと思います。
■市街化調整区域での2種類の住宅
市街化調整区域では、“属人性がある住宅”と“属人性がない住宅”という概念があります。
・属人性がある住宅
属人性がある住宅とは、特定の人のみが住むことを許可された住宅で、特定の用途や人にのみ使用が許されるものです。
具体的には…
・既存権利届により建築された住宅
・世帯構成員等の住宅
・農林漁業従事者のための住宅
・収用移転により建築された住宅
などです。
これらは、特定の状況(職業)にある人が住むことを前提として建てられています。
よって、その人が住んでいない場合には、他の用途での使用が制限されています。
この属人性がある住宅で住宅宿泊事業を展開する場合は、その特定の人が住んでいる必要があるので、いわゆる家主不在型の民泊は不可になります。
・属人性がない住宅
属人性がない住宅とは、その住宅が特定の人だけに利用が許可されているわけではなく、誰でも利用できる状態を指します。
通常の住宅として扱われるため、都市計画法に基づく許可を取得せずに、住宅宿泊事業を展開することが出来ます。
市街化調整区域での民泊運営をする場合は、やはり属人性の有無、都市計画法に基づく開発許可の要否、そして各自治体によるローカルルールを、事前に確認して進める必要がありますね。
樺島 誠二 / プロフィール

- 申請取次行政書士・樺島 誠二(第24091486号)
- 【行政書士✕プロドラマー】
神奈川の二刀流行政書士・樺島 誠二です。
ビザ申請、帰化申請等の国際業務や、民泊申請をメインに、開業2年目ながら、既に多くの案件を受任。
迅速且つ確実な申請サポートを提供します。
また、沢木優の名義でプロドラマーとしても活動中(Pearl Drums、Vic Firth社のモニターアーティスト)です。
2002年にメジャーデビュー後、レコーディングやライヴのサポート、ドラム講師など…数々のドラム仕事を経験。
2024年3月には、New Yorkブロードウェイミュージカル「WITHOUT YOU」来日公演にてツアードラマーを務めました。
最新の投稿
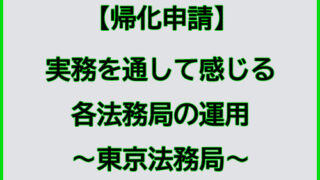 受任実績2026年2月13日【帰化申請】実務を通して感じた東京法務局の運用
受任実績2026年2月13日【帰化申請】実務を通して感じた東京法務局の運用 ドラマー2026年2月12日明日は、ドラム仕事の日
ドラマー2026年2月12日明日は、ドラム仕事の日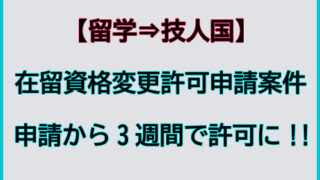 ビザ申請2026年2月10日【留学⇒技人国】申請から3週間で許可が出ました!
ビザ申請2026年2月10日【留学⇒技人国】申請から3週間で許可が出ました! 受任実績2026年2月4日ゴミのルールも厳しい新宿区の住宅宿泊事業
受任実績2026年2月4日ゴミのルールも厳しい新宿区の住宅宿泊事業