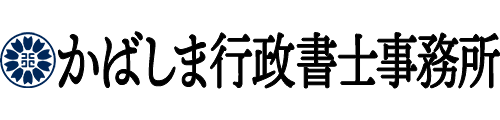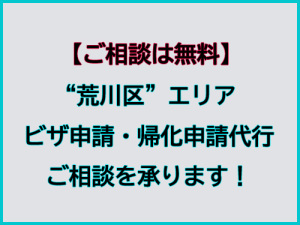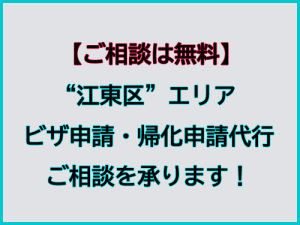ワーキングホリデーとは?
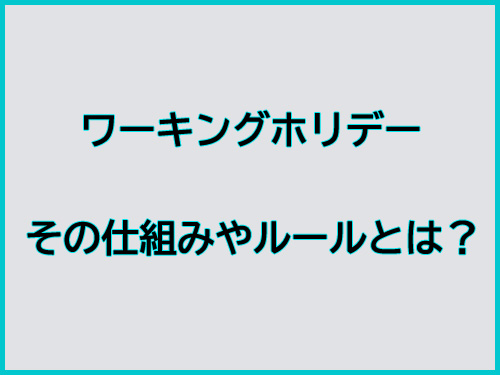
今回は、“ワーキングホリデー”について書いてみます。
トータル3回に分けて書きますが、初回は“ワーキングホリデーとは?”ということで、基本的な仕組みやルールなどを。
ワーキングホリデーで付与される在留資格は、“特定活動告示5号”または、“特定活動告示5号の2”になります。
この在留資格は学歴要件はなく、協定を結ぶ2国間及び地域間での若者の滞在を認める制度で、文化交流や相互理解が目的とされています。
観光ビザや就労ビザ等と違って、ワーキングホリデーには活動の制限がありません。
学業、就労、旅行等のように、ある程度は自由に活動出来るのが魅力の1つでもあります。
■ワーキングホリデーの主なルール
ワーキングホリデーには、協定を結ぶ2国間及び地域間の国民で、一定の年齢制限があります。
また、この制度を利用出来るのは、1か国につき1回のみで、且つ期間は最長で1年です。
よって、在留期間の延長は認められません。
申請については、外国人本人が直接、日本国大使館等に出向き申請する流れとなります。
※ワーキングホリデー対象国については、【こちら】をご確認下さい。
年齢制限に関して、もう少し詳しく書きます。
基本的には、18歳~30歳とされていますが、相手国により違いもあります。
オーストリア、カナダ、韓国の方については、18歳~25歳とされていますが、政府当局が認める場合には30歳以下まで取得可能なケースもあります。
また、アイスランドの方は、18歳~26歳となっています。
■ワーキングホリデーの魅力
何といっても、ワーキングホリデーでは、就労制限がないことでしょう。
留学ビザや家族滞在ビザでは、原則として就労は不可で、資格外活動の許可を得ることで、週28時間までのアルバイトしか出来ません。
その点、ワーキングホリデーでは、職種や雇用形態、労働時間も自由です。
※職種が自由とは言っても、クラブやパチンコ店などの風俗営業関連の職種では就労出来ません。
■ワーキングホリデーの雇用保険と社会保険
ワーキングホリデーで就労した場合、雇用保険への加入は不要です。
在留目的が“休暇”となっているため、ワーキングホリデー所属の外国人は被保険者にはなりません。
一方で、社会保険への加入は必要です。
社会保険には、厚生年金保険、健康保険、労災保険等がありますが、日本人と同様の加入基準が適用されるため、原則として社会保険への加入は必須になります。
例外として、ワーキングホリデーで在留している方が、アルバイトやパートで就労している場合、月の労働時間や日数が通常の社員の4分の3以下であれば、厚生年金保険と健康保険については加入の対象外になります。
ただし、下記の条件を全て満たしている場合には、上記の事情に関係なく厚生年金保険、健康保険への加入は必須となります。
・労働時間が週20時間以上
・就労している会社の規模が501人以上の企業
・1年以上の雇用期間が見込まれる
・月額賃金が8万円以上
・学生ではない
■ワーキングホリデーの所得税率
ワーキングホリデーの所得税率は、固定で20.43%です。
通常、日本人の場合には、累進課税制度が適用されるため、所得額に応じて所得税率は異なります。
しかし、ワーキングホリデーの在留者は、非居住者となるため、累進課税制度は適用されません。
樺島 誠二 / プロフィール

- 申請取次行政書士・樺島 誠二(第24091486号)
- 【行政書士✕プロドラマー】
神奈川の二刀流行政書士・樺島 誠二です。
ビザ申請、帰化申請等の国際業務や、民泊申請をメインに、開業2年目ながら、既に多くの案件を受任。
迅速且つ確実な申請サポートを提供します。
また、沢木優の名義でプロドラマーとしても活動中(Pearl Drums、Vic Firth社のモニターアーティスト)です。
2002年にメジャーデビュー後、レコーディングやライヴのサポート、ドラム講師など…数々のドラム仕事を経験。
2024年3月には、New Yorkブロードウェイミュージカル「WITHOUT YOU」来日公演にてツアードラマーを務めました。
最新の投稿
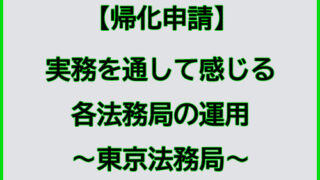 受任実績2026年2月13日【帰化申請】実務を通して感じた東京法務局の運用
受任実績2026年2月13日【帰化申請】実務を通して感じた東京法務局の運用 ドラマー2026年2月12日明日は、ドラム仕事の日
ドラマー2026年2月12日明日は、ドラム仕事の日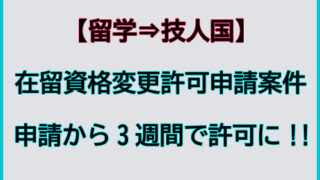 ビザ申請2026年2月10日【留学⇒技人国】申請から3週間で許可が出ました!
ビザ申請2026年2月10日【留学⇒技人国】申請から3週間で許可が出ました! 受任実績2026年2月4日ゴミのルールも厳しい新宿区の住宅宿泊事業
受任実績2026年2月4日ゴミのルールも厳しい新宿区の住宅宿泊事業